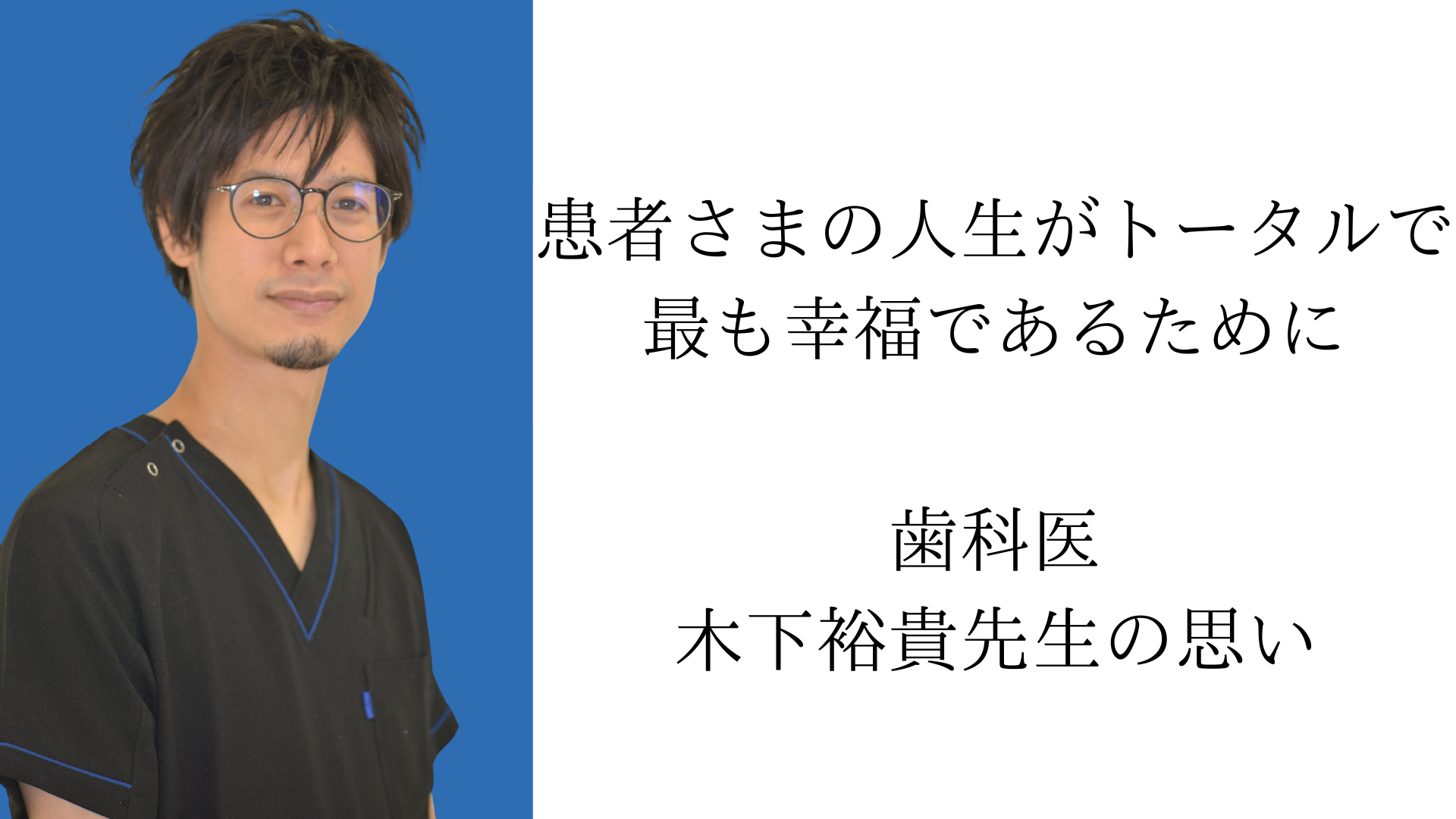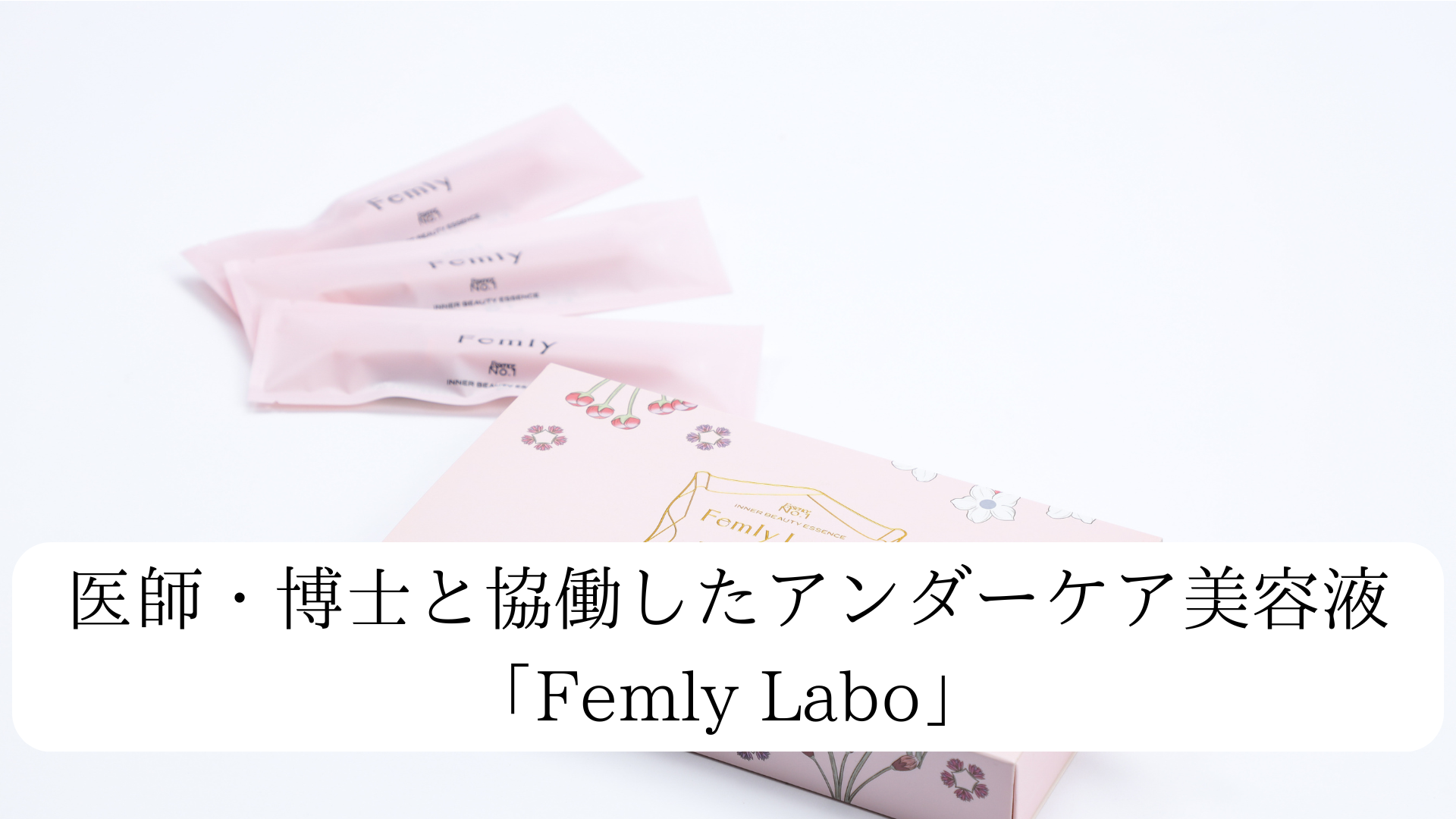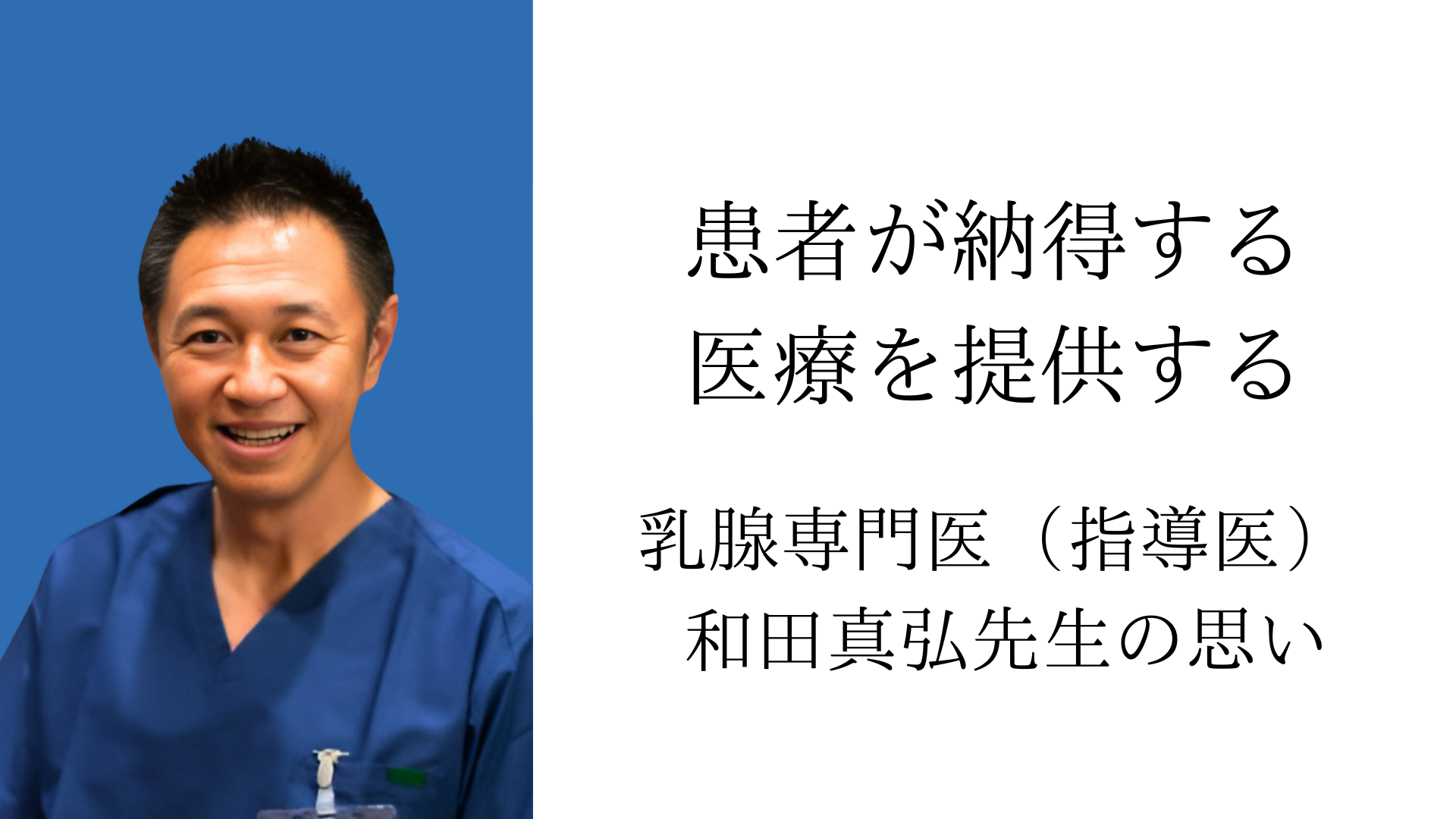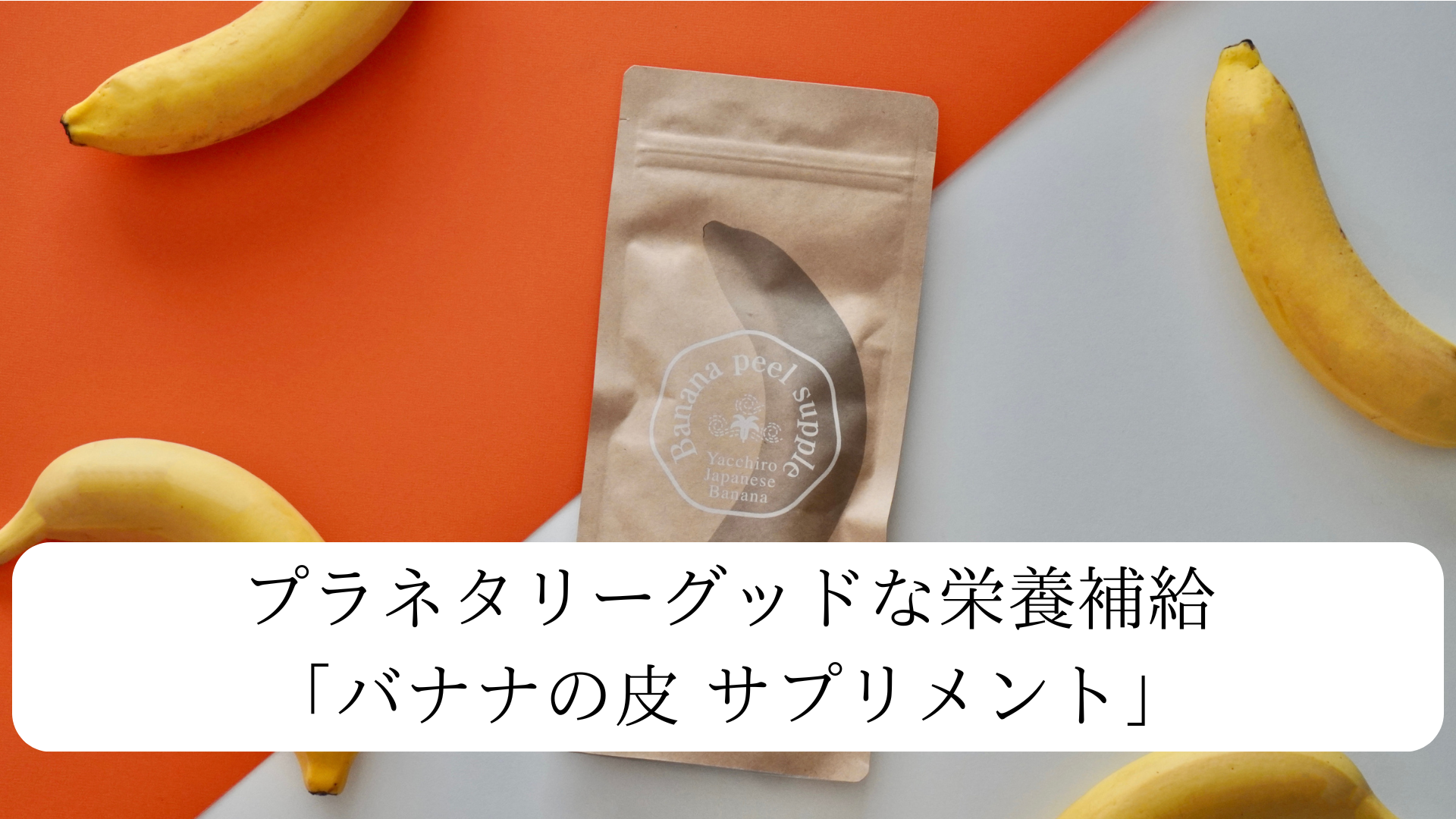辛い目の乾き・ドライアイは治せる?



監修医師:郷 正憲(徳島赤十字病院)
保有免許・資格は日本麻酔科学会専門医、ICLSコースディレクター、JB-POT。主な著書は『看護師と研修医のための全身管理の本』。

日本におけるドライアイの患者数は約2200万人といわれています。
ドライアイは年齢に関係なく誰もが起こりえる目の病気の一つです。特にスマホやパソコンを使用する機会が多い方は「VDT症候群」によりドライアイを発症するケースも多くみられます。
目の乾きや目の疲れなどの症状に対し、市販の点眼薬を使用している人も多いかもしれませんが、市販の点眼薬ではドライアイの根本的な治療にはなりません。「ただの目の乾き」だと軽く考えてしまう方もいるかもしれませんが、ドライアイは放置していると角膜炎や結膜炎を引き起こす恐れもあり、眼科で適切な検査・治療を受けることが重要です。
ここでは医師監修のもと、ドライアイとは何か、そして最新の治療と費用について詳しく解説していきます。
ドライアイとは

ドライアイとは、さまざまな要因により涙の分泌量の低下や成分の変化が起こり、目の表面の水分保持バランスが崩れることで目が乾燥する状態をさします。ドライアイになると、目の表面を守る角膜に傷がつきやすくなり、目の不快感や、視力低下などを引き起こす恐れがあります。
ここでは、ドライアイの症状と原因について詳しく解説していきます。
ドライアイの症状
ドライアイの主な症状は以下の通りです。
- 目が乾く感じがする
- 充血する、目やにが出る
- 目がごろごろして不快感がある
- 視界が霞んでよく見えない
- 光がまぶしく感じる
- 目の疲れが取れず、頭痛がする など
ドライアイの症状は人それぞれ異なります。軽度のドライアイであれば、目の乾き自体よりも目の疲れやすさやゴロゴロした感じを自覚症状として訴える方も多いです。
ドライアイにより目の表面が乾燥した状態が続くと、角膜が傷つきやすくなってしまいます。そしてその状態のまま放置していると次第に炎症が起こり、悪化すると角膜炎、結膜炎などに移行するケースも多いため、注意が必要です。
ドライアイの原因
ドライアイを起こす原因として、大きく「涙液減少型」と「蒸発亢進型」の2種類に分けられます。それぞれの違いについてみていきましょう。
涙液減少型
涙液減少型とは、涙を作る涙腺の機能低下や破壊などにより、涙を作る量が少なくなることで生じるドライアイのことです。
涙液減少型のドライアイは、主に涙腺の機能の低下や加齢に伴い起こることが多いです。また糖尿病やその他の病気(シューグレーン症候群など)、レーシックの副作用などでも発症することがあります。
蒸発亢進型
蒸発亢進型とは、涙が目の表面に留まる事ができず、すぐに乾いてしまうことで生じるドライアイのことです。
近年、さまざまな研究から蒸発亢進型のドライアイを引き起こす主な原因は「マイボーム腺機能不全(MGD)」であることが分かりました。
マイボーム腺とは、まぶたの縁にある皮脂腺の一つのことです。通常は目の表面で涙が蒸発しないようにマイボーム腺から油分が分泌されるのですが、さまざまな要因により十分な油分が分泌されず、涙が蒸発しやすくなることをマイボーム腺機能不全(MGD)といいます。
また外的な要因としては、パソコンやスマホの長時間の使用、コンタクトレンズの使用、エアコンの送風など挙げられます。
ドライアイ検査と診断基準

ドライアイが疑われる場合、一般的に眼科では「シルマーテスト」もしくは「BUT測定テスト」を行い、ドライアイの診断をします。
シルマーテスト
シルマーテストとは、涙の分泌量を測定する検査方法です。
シルマーテストでは、下まぶたにろ紙を挟んだまま5分間置きます。ろ紙が涙で濡れた範囲を測定し、5mm以下であればドライアイと診断されます。(正常値:10mm以上)
BUT測定テスト(涙液層破壊時間)
BUT測定テストとは、涙の質を測定する検査方法です。
BUT測定テストでは、フルオレセインという点眼薬を用いて涙の色を染めます。そのまま10秒間まばたきをせずに目を開けたまま、涙の質の変化をチェックします。
2016年以前は、上記2種類の検査方法を用いてドライアイの確定診断が行われていました。しかし2016年にドライアイ研究会が発表した「日本のドライアイの定義と診断基準の改訂」により、「シルマー検査」は必須ではなくなり、新たに以下の診断基準が定められています。
ドライアイの診断基準
以下の2項目の両方に該当する場合、ドライアイと診断されます。
- 眼不快感,視機能異常などの自覚症状
- 涙液層破壊時間(BUT)が 5 秒以下
(参考:2016年ドライアイ研究会「日本のドライアイの定義と診断基準の改訂」)
ドライアイ治療と費用

上記の検査によりドライアイと診断された場合は、「点眼療法」「IPL療法」「涙点プラグ療法」などを用いた治療が行われます。
ここでは、それぞれの治療と費用について解説していきます。
点眼療法
ドライアイの診断がおりると、一般的に点眼療法(目薬)による治療が行われます。
点眼療法では、目の状態に合わせた点眼薬を使用します。ドライアイ治療では、目の水分保持を目的とした、涙液に近い成分の点眼薬を使用するケースが多いです。また目に炎症をきたしている場合は、レバミピド点眼薬やステロイド点眼薬を用いることもあります。
点眼薬を使用してもドライアイの症状が改善しない場合や、症状が悪化するような場合は、IPL療法や涙点プラグ療法レーザー治療が検討されます。
IPL療法
IPL療法とは、油分の分泌を行うマイボーム腺にレーザーを照射し、涙の油分と水分量の調節を円滑にする治療方法です。これにより涙の油分と水分量のバランスが保たれ、ドライアイ症状の改善が期待されます。
IPL療法は約10分程度で終わるため、日帰りの外来で行える治療方法となります。
IPL療法の費用(自費診療)
約10,000円〜15,000円(1回あたり)
IPL療法は、1回目の治療後3~4週間の間隔を空けて、合計2~4回程度行うことでドライアイの症状が改善していきます。
もし4回行っても症状の改善がみられない場合は、5回目以降の治療も可能です。
涙点プラグ療法
涙点プラグ療法とは、涙の排出口である「涙点」に小さなプラグ(栓)を挿入し、目の潤いを保つ治療方法です。
涙点プラグ療法で使用されるプラグの種類は主に「シリコンプラグ」と「コラーゲンプラグ」の2種類があります。
シリコンプラグは、直径0.5~1mm程度の小さいシリコンを挿入し、涙点にフタをします。涙点プラグ療法として従来から使用されてきた治療方法となりますが、人によってはシリコンの違和感などが生じることもありました。
それに対しコラーゲンプラグは、体温で硬化する液体コラーゲンを注入し、涙液が流れ出るのを防ぐ、新しい治療方法です。ただし、約2〜3ヶ月経過するとコラーゲンが体内で分解され排出されてしまうため、持続効果が短く、定期的な注入処置が必要です。
どちらも外来処置が可能であり、ほとんどの場合体への負担も少ないといわれています。
涙点プラグ療法の費用(3割負担の場合)
約5,000円〜7,000円(1回あたり)
まとめ
ドライアイは、目の乾きや目の疲れやすさといった症状が、持続する目の病気です。
軽度の症状だからと放置したままにしていると、目の炎症にもつながり、新たな目の病気を引き起こしてしまう可能性があるため注意が必要です。
ドライアイの治療は保険適用もあり短時間の外来処置が可能なため、比較的受けやすい治療であるといえるでしょう。少しでも気になる症状があれば、一度眼科を受診することをおすすめします。



.jpg) 郷 正憲(徳島赤十字病院)
郷 正憲(徳島赤十字病院)