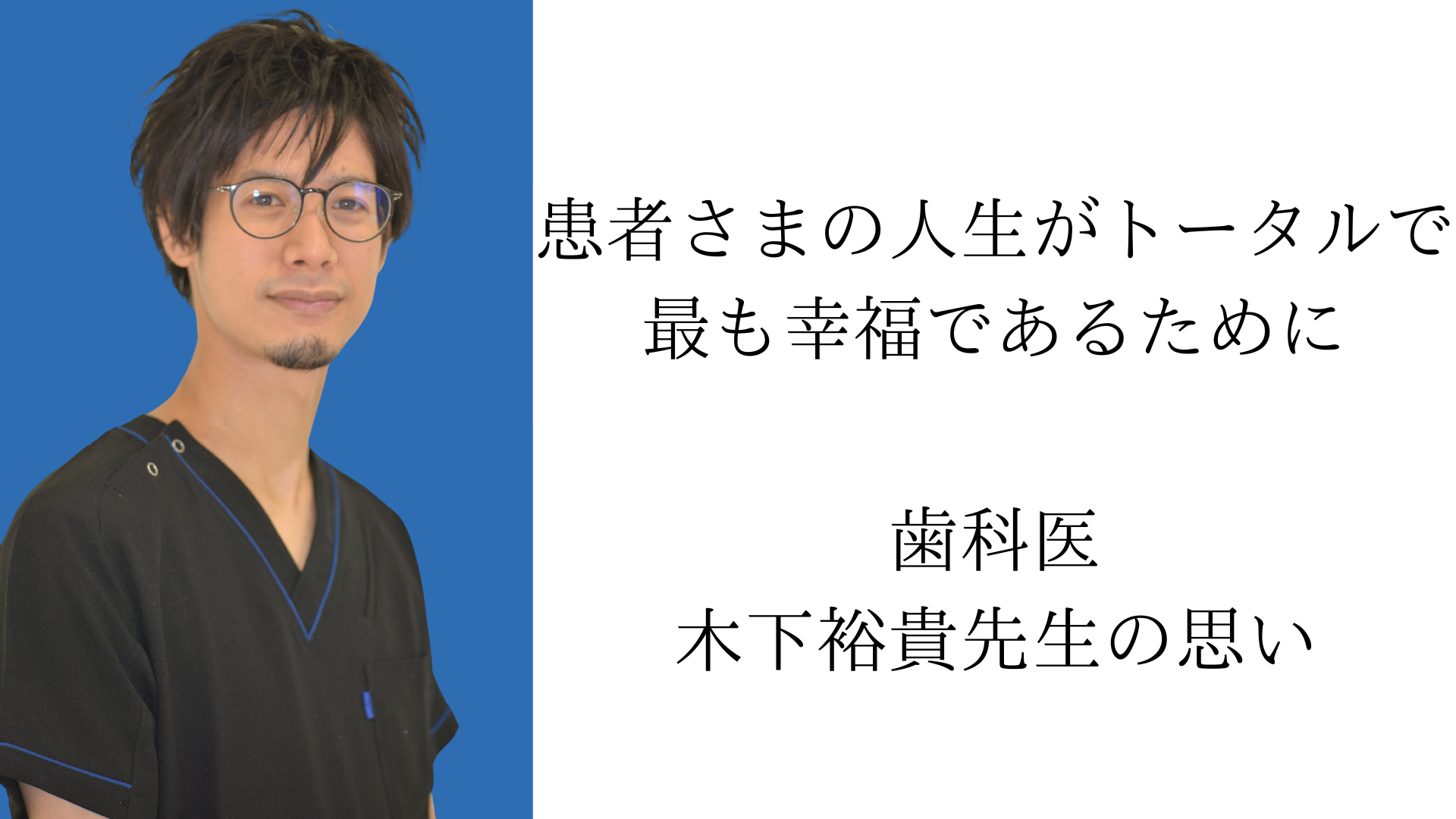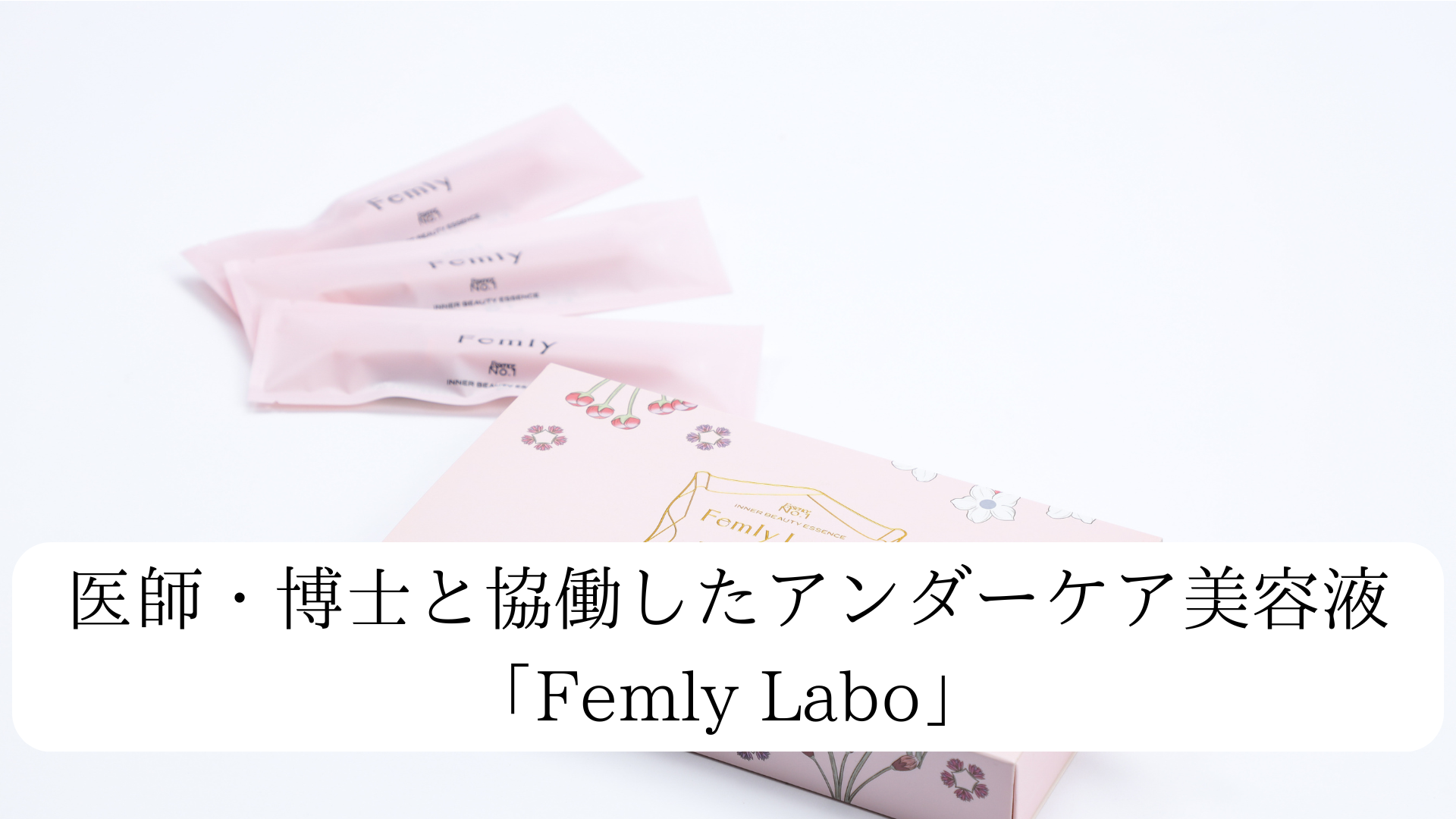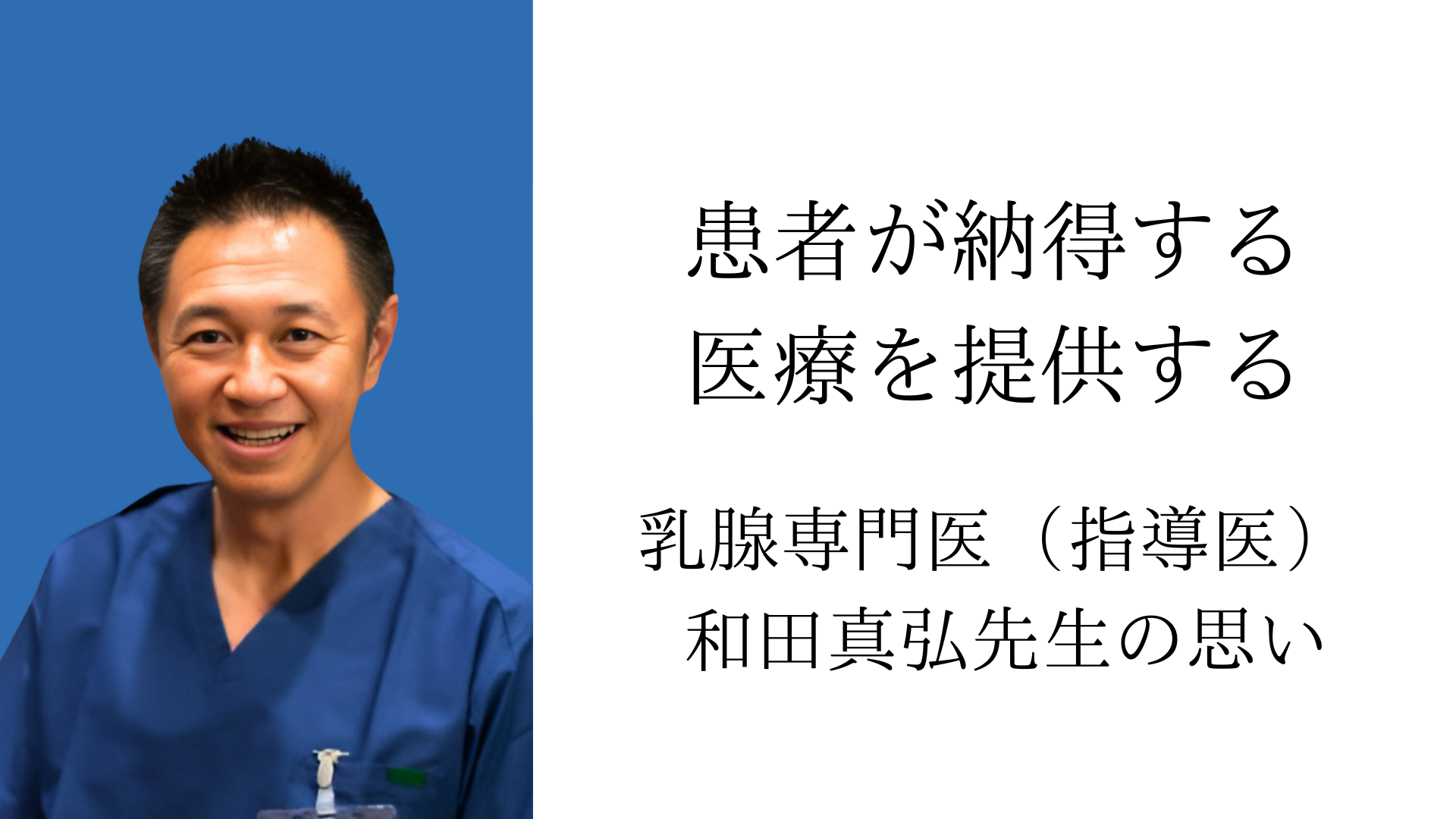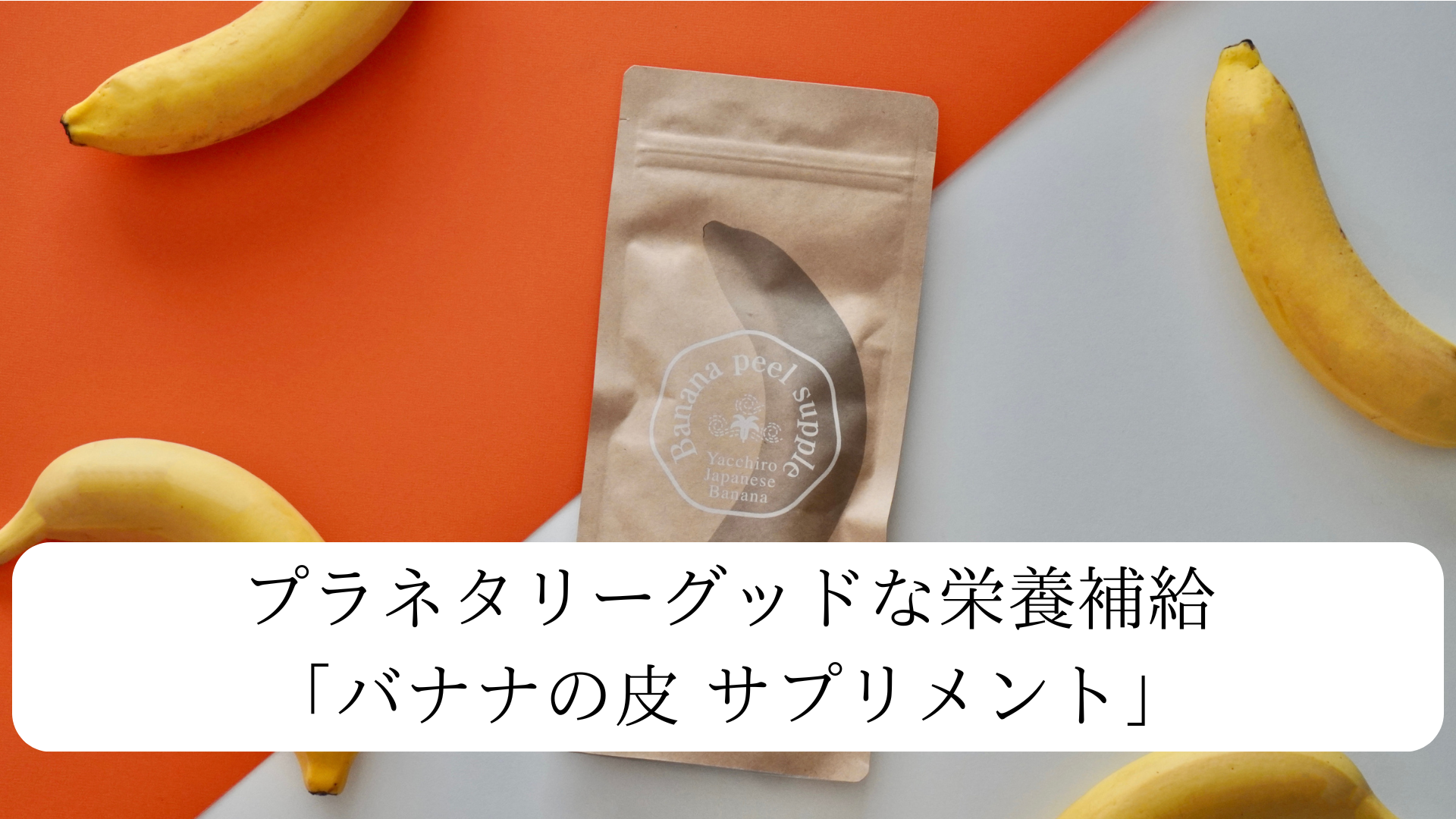ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは~最新治療と気になる費用~



監修医師:中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター)
兵庫医科大学卒業。米国内科学会上席会員、日本内科学会総合内科専門医などの資格を保有。
主な研究内容・論文は「生活習慣関連因子と大腸カプセル内視鏡検査」。
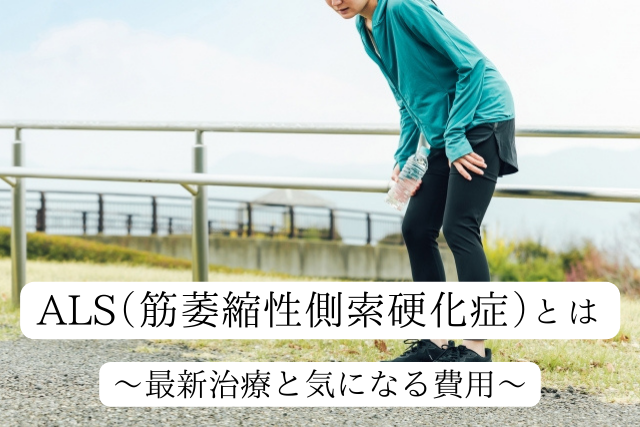
ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは、国の指定難病に認定されている、全身の筋肉が徐々に動かなくなる病気のことです。
以前はALSというと「呼吸ができなくなって死ぬ病気」との認識がありましたが、現在呼吸管理や栄養補助の方法などの発達により、長期療養が可能となりました。
ここでは、医師監修のもとALSとは何か、そして治療や治療費について詳しく解説していきます。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは

ALSは日本語では「筋萎縮性側索硬化症」といい、全身の筋肉が徐々に動かなくなる病気です。
ALSを発症すると、脳から脊髄、脊髄から末梢神経の運動神経系が障害を受け、筋肉に「動かせ」という指令が伝えられなくなります。それにより筋肉が徐々に痩せていき、体が動かしにくくなったり、食べ物を飲み込みにくくなったりといった症状があらわれます。
現在日本におけるALSの患者数はおよそ1万人、年代別で見ると40~50代以降で増え始め、60代以降がおよそ8割を占めます。(参考:ALSに関するデータ | JALSA / 日本ALS協会 (alsjapan.org))
ALSの原因
ALSの原因はまだ十分に明らかにされていません。
現在のところALS患者全体のうちおよそ5~10%は、遺伝子の異変によるもの(家族性ALS)であることが分かっています。
残りの約90~95%は遺伝性ではなく、「グルタミン酸の過剰分泌が神経細胞を壊すこと」や「酸化ストレスが運動神経細胞などの酸化的障害を起こすこと」などが原因となって発症するのではないかと考えられています。
ALSの症状
ALSは脳や脊髄の運動神経系が障害を受けて筋肉が痩せていき、徐々に体が動かなくなる病気です。
ALSの初発症状はどこの部位から発症するかによって、以下の4つに分類されます。
- 上肢型:字が書きにくい、腕が上げにくい など
- 下肢型:歩きにくい、階段が昇りにくい など
- 球麻痺(きゅうまひ)型: 飲み込みが悪くなる、言葉が話しにくくなる など
- 呼吸筋麻痺型:呼吸困難が先にあらわる
上記のうち、全体の約3/4程度の患者さんは上肢型・下肢型、つまり手足に力が入りにくくなる症状から発症します。
残りの約1/4の患者さんは球麻痺型、そして約2%の患者さんは手足の筋力低下より先に呼吸困難の症状があらわれる呼吸筋麻痺型となります。
ALSの四大陰性症状
ALSは体のさまざまな所に症状があらわれますが、一方で末期まで出現しにくい症状もあります。
これを四大陰性症状といい、具体的には以下の4つを指します。
- 膀胱直腸障害
- 眼球運動障害
- 感覚障害
- 褥瘡(床ずれ)
膀胱直腸障害
膀胱、直腸の筋肉を動かす神経は障害されず、機能が温存されるケースが多いです。
尿意や便意の感覚も正常なので、介助してもらって自分で用を足すことができます。
眼球運動障害
眼球を動かす神経は障害されず、機能が温存されるケースが多いです。
話すことや、手や指を動かすことが出来なくなっても、瞬きと眼球の動きだけで意思表示をすることができます。
感覚障害
視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚などの知覚神経は障害されず正常なまま維持されるケースが多いです。
褥瘡(床ずれ)
通常寝たきりの状態になると床ずれができてしまいますが、ALS患者さんでは寝たきりの状態になっても、床ずれになりにくいと言われています。
ALSの経過について

ALSは進行性の病気のため、症状が良くなることはありません。
ALSの症状は、手や足に力が入りにくくなったり、舌や口が動きにくくなったりして始まり、ALSを発症してから2〜4年位で全身の筋力が弱くなって声を出しにくくなり、食べ物や水さえも飲み込めなくなります。
それと並行して歩けなくなり、呼吸も十分にできなくなり、何もしなければ死に至るのです。
症状の進行には個人差があり、10年以上の長期にわたる方もいます。
ALSの治療と費用

ALSは現在のところ原因がはっきりとは分かっておらず、現在のところALSの根治治療は存在しません。
治療の主な目的はALSの進行を遅らせることと、さまざまな症状を和らげることです。
以前はALSというと「呼吸ができなくなって死ぬ病気」といわれていましたが、現在では治療の選択肢が広がり、早期に適切な治療を行えば長期療養も可能になってきました。
ここでは、ALSの治療と治療費について詳しく解説していきます。
ALSの進行を遅らせる
ALSの進行を遅らせるための薬剤は国内では以下の2種類のみとなります。
リルゾール
グルタミン酸による興奮毒性を抑え、神経細胞を保護する内服薬
エダラボン
運動神経細胞などの酸化的障害を抑える
※これまで注射薬のみ承認されていたが、2023年3月から内服薬も販売開始
アメリカでは2022年にレリブリオ、2023年にトフェルセンという新薬が承認され、現在日本での早期承認が待たれているところです。
栄養療法
ALS患者は、通常量の食事をしても体重が減り続けていってしまいます。体重が減る割合が大きいとALSの進行が速くなるため、できるだけ体重を維持していくことが重要です。
体重を維持するためには、高カロリー、高タンパク質の食事、ビタミン、ミネラルを摂るようにしましょう。また食べ物が飲み込みづらくなってきた場合には、経鼻栄養チューブや胃ろう(胃に管を入れて直接栄養を注入する方法)を用いて栄養の補給を行うことが検討されます。
ALSの症状を和らげる
ALSでは進行に伴い、呼吸困難や筋肉の痛み、食事が飲み込みにくくなるなどの症状があらわれます。またALSの患者さんはうつ病になりやすいという報告もあり、人によっては精神的症状がみられる方もいます。
こういった症状をできるだけ緩和させ、患者さんの苦痛を軽減させるための治療が行われます。具体的には、呼吸困難の症状に対する人工呼吸器や、筋肉の痛みの症状に対するリハビリや鎮痛薬、不安や抗うつの症状に対する安定剤や抗うつ剤などが挙げられます。
ALSの治療費
ALSは指定難病のため、国から医療費の助成を受けることができます。
基本的に、ALSの方は自己負担が2割(1割負担の人は1割)になりますが、特定疾患医療費の支給認定を受けた場合、所得や状態に応じて1,000円(人工呼吸器装着者)〜30,000円の自己負担上限額が設けられています。
その他にも、傷病手当や障害年金、心身障害者福祉手当、特別障害者福祉手当などさまざまな支援が受けられることもあるため、詳しくは自治体の福祉課やケアマネージャーなどに相談してみましょう。
まとめ
ALSは脳や脊髄の運動神経系が障害を受けて筋肉が痩せていき、徐々に体が動かなくなる病気です。
原因はいまだはっきりとは解明されておらず、国の指定難病に認定されています。
現在のところALSを根治させる治療法は存在せず、進行を遅らせるための薬物療法と対症療法が中心となってきます。
ただし呼吸管理や栄養管理の方法が発達したために、適切な治療を受けることで長期療養も可能になってきました。
また2022年、2023年にはアメリカで2件の新薬が承認され、今後日本で承認されれば、さらに治療の選択肢が広がっていくことになるでしょう。



-scaled.jpg) 中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター)
中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター)